中古車購入チェックポイント
更新日:2022.01.06 / 掲載日:2022.01.06
中古車ってどれくらい乗れるの?寿命や耐用年数の見分け方を確認しよう!
車も消耗品ですので、当然「寿命」や「耐用年数」があります。
寿命や耐用年数は登録後10年、走行距離数10万キロというのが目安とされていますが、最近の車は質がいいので寿命も長く、メンテナンス次第というところもあります。
ここでは、車の寿命についての通説と実状、また長く乗った場合に発生してくる注意点などを解説していきましょう。あわせて、中古車を購入する人から見て何年落ちの車がちょうどいいのかについても説明します。
しかし、この目安の根拠はどこにあるのでしょう?
実は、車の寿命が10年あるいは走行距離10万キロメートルされているのは日本だけです。外国では中古の日本車が大人気ですが、20年、30年を超えても走っている車は普通に存在しています。
日本車の品質や耐久性は世界でも群を抜いており、メンテナンスがしっかりしていれば、目安とされている数値を超えても問題はないとされています。
では、寿命が10年あるいは走行距離10万キロメートルと言われているのはなぜなのか、解説をしていきましょう。

10年という数字を意識しているのはユーザーに限りません。法律では、日本国内で製造販売された製品についてメーカーは10年間責任を負うと定めていますし、中古車市場でも10年超の車は価値が下がります。
また、新車の発売に合わせて部品メーカーは純正部品を用意し、自動車メーカーは契約に基づいてそれを調達できるようにしますが、その契約期間はおおむね10年です。よって、その後は修理やパーツ交換が難しくなるのです。

実際にはもっと走ることも可能ですが、それでも10万キロという数字には一応の根拠があります。
車の年間の平均走行距離は1年に1万キロとされているので、車が寿命を迎えるもう一つの目安である「10年」に達すれば、走行距離も10万キロです。つまり、10万キロという走行距離は10年という使用年数に匹敵します。
実際、エンジンは10万~15万キロの走行で限界を迎えることが多いですし、修理や交換を行うとしても純正部品はおおむね10年で生産終了となります。そうなると、維持管理だけでもかなりの負担になるでしょう。
しかし、エンジンなどの各パーツをこまめに手入れし、部品の劣化を見逃さずに交換していれば、車の寿命はもっと延ばすことができます。
「10年」「走行距離10万キロ」というのは、最低限の整備点検しか行わない場合の数字と言ってもいいでしょう。
ただ、10万キロを超えてくると故障のリスクが高くなるのは事実で、メンテナンスに高額な費用がかかることもあります。中には丸ごとの交換で10万円以上かかる部品もあり、修理内容によっては中古車を買った方が安く済むこともあるでしょう。
こまめにメンテナンスを行えば、確かに走行距離は伸ばすことができます。しかし、車の細かい維持管理に慣れていない方は、安全のためにも10万キロを一つの区切りと考えるのが賢明です。
2016年の調査によると、車の平均使用年数は12.76年だったので、今は約13年というのが一般的と言えそうです。
1975年頃の平均使用年数は約7年なので、40年の間に約6年も車の平均寿命が延びたことになります。
寿命が10~13年というのは短いと思われるかも知れませんが、技術の発達によって車の寿命はどんどん延びてきています。
また、交通インフラの発達により、都会では頻繁に車に乗る必要がなくなったことも平均使用年数が延びた一因でしょう。乗る頻度が減れば、車や部品が消耗せず長持ちすることになります。
一方でバブル崩壊以降の可処分所得が増えていないため、車の買い替えを控えているということも平均保有年数を延ばしている一因とも言われています。
現代は高性能の車が多く、10年を過ぎても問題なく走れる車種は珍しくありません。それにもかかわらず中古車市場では10年を境に車の価値が大きく下がるので、こうしたギャップがある限り「寿命は10年」というイメージはすぐには変わらないでしょう。
この数字は一律で決められていますが、そもそもは税法上の計算に基づくもので、車体やパーツの耐用年数を厳密に測定したものではありません。よって、実際にはそれぞれの車によって耐用年数は変わってくるでしょう。
現代の車は昔と比べて性能が段違いに向上しており10年以上乗れることも珍しくないため、耐用年数が実態に即していないケースも多くあります。
しかし、国が公に定めている標準的な数字である以上、一つの基準にはなります。車の寿命を考える上での目安にするのもいいでしょう。
では具体的に、耐用年数はどのように算出されるのでしょう?
中古の普通自動車の耐用年数は、新車登録から6年が経過しているかがポイントになります。
6年以上であれば耐用年数は「法定耐用年数×0.2」で割り出されます。
6年未満であれば耐用年数は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」で計算されます。

以下では、特に細かい点検や交換が必要な部品について、その耐用年数とあわせて説明していきます。
タイミングベルトが断裂するとエンジンが故障するので、交換・修理費用は高くつきます。走行距離が10万キロ未満でも断裂するケースがあるので、あまり走っていないからと言って油断はできません。
走行中にタイミングベルトが切れれば他の部分にも影響を及ぼして、最悪の場合「出火」することもあります。
タイミングベルトの特徴は、断裂するとエンジンを始めとする他の部品にも故障が発生するという点です。それらの修理費用を全て合わせると20万円を超すこともあるので、普段からメンテナンスが重要です。
また、金属製のタイミングチェーンを採用した車も近年増えてきています。タイミングチェーンは10万キロで交換の必要がなく、断裂の危険性も極めて少ないので中古車選びをする際にはタイミングチェーンを搭載した車で検討するのもいいでしょう。
交換にかかる費用は決して高額ではないものの、工賃がおおむね2,000円程度なのに対し、バッテリー本体の価格はかなり幅があるため一概には言えません。
バッテリーも走行に欠かせないアイテムで、止まってしまうと電力供給がストップし、車は止まってしまいます。その一方で非常に消耗が激しく、車に長く乗りたいのであればこまめな点検や交換が欠かせません。
バッテリーは使えば使うほど劣化しますが、逆に全く使わなくても劣化が進むので注意が必要です。車を運転すること自体がバッテリーの寿命を延ばすことにつながるので、定期的にエンジンをかけて走行するようにしましょう。
基本的には低燃費のタイヤの方が寿命は短めだと言える程度で、雪道や未舗装の道を走る機会があるかどうかでも変わってきます。
タイヤの溝は走るたびに摩耗しますが、すり減り具合を知らせてくれるのがスリップサインです。新品は溝が8mmですが、摩耗が進んで1.6mmになるとスリップサインが露出してくるので、1ヶ所でも露出が確認されたタイヤは早めに交換しましょう。
溝がないタイヤで走ると制動距離が長くなり、路面状況によってはスリップしやすくなるので大変危険です。また、そのまま放置していると車検も通りませんし、最悪の場合反則金の支払いや違反点数の累積を受けることもあります。
タイヤはゴムでできているので経年劣化は避けられません。ひび割れが発生すると、走行中にバーストする危険性もあります。
このように自動車の寿命が延びているのは、自動車製造の技術や安全性の向上によるところが大きいでしょう。故障や事故が減少して、車も安定的に乗り続けられるようになっています。
かつて、乗用車は7年程度で買い替えるのが一般的でした。しかし、現在は10年以上乗っても、また10万キロ以上走行しても、状態によっては中古車として高額で買い取られることもありますし、その程度なら日本製の中古車は海外では普通に乗られています。
メンテナンスや部品の交換次第で10年でも20年でも乗れるのは頼もしい限りですが、どうなった時点で寿命と捉えるか、という問題もあります。人によっては修理費用が多くかかるようになったら寿命、と考えることもあるでしょう。
しかし、今は技術力の向上によって、10年経っても美しい状態を保ち、安定的に走れる車が増えています。
走行距離が10万キロを超えても、こまめにメンテナンスを行えば中古車として高く売れる場合もあります。
通常、日本ではパワーウインドウやエアコンは最初から本体に付いていますが、海外ではそれらは標準装備ではありません。その分の付加価値が高くなるのに加えて、日本車はその燃費の良さと耐久性ゆえに評価が高いのです。
耐用年数が長く、オプション付きで燃費の良さは世界一とまで言われる日本車は、こうした理由から海外での需要が高まっています。
日本で新車登録された車の3分の1が海外に出ているほどで、最近は東南アジアにも販路が拡がっています。
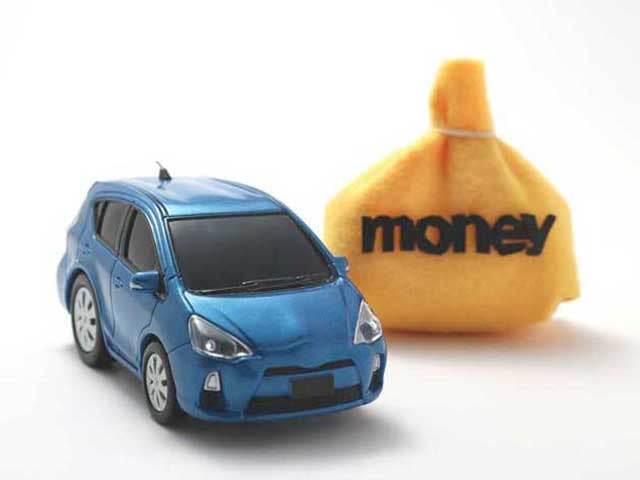
もちろん、長く乗ればそれだけ部品の劣化が進んで故障しやすくなりますし、定期的に部品交換や修理を行わなければなりません。
もっと長く乗るためには、具体的にどんな点に注意するべきなのでしょう?
もしも海外に販売ルートを持っている買取業者であれば、古い車でも比較的高値で買い取ってもらえる可能性があります。
しかし、国内のみの販路しかない業者であれば、高値で売却することについてはあまり期待はできないかもしれません。
しかも、普通車の場合は新車登録から13年が経つと自動車税の税額もアップします。
また、10年以上が経った車でマイナーチェンジやフルモデルチェンジが行われていたりすると、純正の部品が入手しづらく部品代が高くつくこともあるでしょう。
古くなると燃費も悪くなり、全体的にお金がかかるようになります。

それは、車検のタイミングで車を売却する方が多く、車の種類や数が多いからです。
ローンや残高設定型クレジットは支払期間が5年に設定されているケースが多いため、返済が終わったタイミングで売られた車もよくあります。
3年と5年という数字は、車のメーカー保証の期間とも重なります。一般保証が3年、特別保証が5年なので、この保証が切れるタイミングで車を買い替える方も多いです。
さらに、7年目あるいは9年目の車検のタイミングになると車を買い替える方はもっと増えるので、この年式の中古車は流通量も格段に多いです。
これらの年式を基準に中古車を探すと、安い良質なものを見つけやすくなるでしょう。
もちろん10年が経った車だから故障ばかりするとは言い切れませんが、故障が起きても対処できるように準備はしておきましょう。
大切なのは、「走行距離」「年式」「整備状況のバランス」を考えて購入することです。
ただし、整備状況や安全性について素人が確認するのは難しいので、購入前に販売店側とよく話し合っておくことをおすすめします。
購入後の故障などのリスクをできるだけ避けるには、メンテナンスや修理、部品交換をこまめに行うことが大切です。
これらの注意点を念頭に置いておけば、10年落ちの車でも掘り出し物を見つけられるかもしれません。
寿命や耐用年数は登録後10年、走行距離数10万キロというのが目安とされていますが、最近の車は質がいいので寿命も長く、メンテナンス次第というところもあります。
ここでは、車の寿命についての通説と実状、また長く乗った場合に発生してくる注意点などを解説していきましょう。あわせて、中古車を購入する人から見て何年落ちの車がちょうどいいのかについても説明します。
この記事の目次
車の平均寿命はどれくらい?
車の平均寿命は「初回登録から10年」「走行距離10万キロメートル」が目安とされており、これらの段階に達すると販売店から買い替えをすすめられることも多いかもしれません。しかし、この目安の根拠はどこにあるのでしょう?
実は、車の寿命が10年あるいは走行距離10万キロメートルされているのは日本だけです。外国では中古の日本車が大人気ですが、20年、30年を超えても走っている車は普通に存在しています。
日本車の品質や耐久性は世界でも群を抜いており、メンテナンスがしっかりしていれば、目安とされている数値を超えても問題はないとされています。
では、寿命が10年あるいは走行距離10万キロメートルと言われているのはなぜなのか、解説をしていきましょう。
「初回登録から10年」が買い替えの目安とされている

10年という数字を意識しているのはユーザーに限りません。法律では、日本国内で製造販売された製品についてメーカーは10年間責任を負うと定めていますし、中古車市場でも10年超の車は価値が下がります。
また、新車の発売に合わせて部品メーカーは純正部品を用意し、自動車メーカーは契約に基づいてそれを調達できるようにしますが、その契約期間はおおむね10年です。よって、その後は修理やパーツ交換が難しくなるのです。
車は何キロ走ると寿命になる?

実際にはもっと走ることも可能ですが、それでも10万キロという数字には一応の根拠があります。
車の年間の平均走行距離は1年に1万キロとされているので、車が寿命を迎えるもう一つの目安である「10年」に達すれば、走行距離も10万キロです。つまり、10万キロという走行距離は10年という使用年数に匹敵します。
実際、エンジンは10万~15万キロの走行で限界を迎えることが多いですし、修理や交換を行うとしても純正部品はおおむね10年で生産終了となります。そうなると、維持管理だけでもかなりの負担になるでしょう。
寿命の目安は「走行距離10万キロ」
このように、車は約10万キロ、よくても15万キロの走行距離が寿命の目安と考えられます。そのため、この限界のタイミングに差しかかって故障する前に、先回りする形で買い替える方も多いかもしれません。しかし、エンジンなどの各パーツをこまめに手入れし、部品の劣化を見逃さずに交換していれば、車の寿命はもっと延ばすことができます。
「10年」「走行距離10万キロ」というのは、最低限の整備点検しか行わない場合の数字と言ってもいいでしょう。
メンテナンス次第では20万キロ走ることは可能
車が寿命を迎える走行距離は10万キロというのが一般的ですが、メンテナンス次第で延ばすことも可能です。うまくいけば20万キロ以上走ることもあり、一概に10万キロを超えたから廃車にすべきとは言えません。ただ、10万キロを超えてくると故障のリスクが高くなるのは事実で、メンテナンスに高額な費用がかかることもあります。中には丸ごとの交換で10万円以上かかる部品もあり、修理内容によっては中古車を買った方が安く済むこともあるでしょう。
こまめにメンテナンスを行えば、確かに走行距離は伸ばすことができます。しかし、車の細かい維持管理に慣れていない方は、安全のためにも10万キロを一つの区切りと考えるのが賢明です。
寿命とされる年数は?
結局のところ、車の寿命は何年くらいと考えるといいのでしょう?2016年の調査によると、車の平均使用年数は12.76年だったので、今は約13年というのが一般的と言えそうです。
1975年頃の平均使用年数は約7年なので、40年の間に約6年も車の平均寿命が延びたことになります。
寿命が10~13年というのは短いと思われるかも知れませんが、技術の発達によって車の寿命はどんどん延びてきています。
また、交通インフラの発達により、都会では頻繁に車に乗る必要がなくなったことも平均使用年数が延びた一因でしょう。乗る頻度が減れば、車や部品が消耗せず長持ちすることになります。
一方でバブル崩壊以降の可処分所得が増えていないため、車の買い替えを控えているということも平均保有年数を延ばしている一因とも言われています。
寿命の目安は「10年」
これまでは「車の寿命は10年」というのが定説でした。その大きな理由の一つとして、車の部品には10年を目安に交換が必要になるものが多い、ということが挙げられます。現代は高性能の車が多く、10年を過ぎても問題なく走れる車種は珍しくありません。それにもかかわらず中古車市場では10年を境に車の価値が大きく下がるので、こうしたギャップがある限り「寿命は10年」というイメージはすぐには変わらないでしょう。
国が定めた「法定耐用年数」も存在する
自動車には耐用年数、あるいは法定耐用年数と呼ばれる数字があり、「普通自動車は6年」「軽自動車は4年」とされています。この数字は一律で決められていますが、そもそもは税法上の計算に基づくもので、車体やパーツの耐用年数を厳密に測定したものではありません。よって、実際にはそれぞれの車によって耐用年数は変わってくるでしょう。
現代の車は昔と比べて性能が段違いに向上しており10年以上乗れることも珍しくないため、耐用年数が実態に即していないケースも多くあります。
しかし、国が公に定めている標準的な数字である以上、一つの基準にはなります。車の寿命を考える上での目安にするのもいいでしょう。
事業用の車は「法定耐用年数」から寿命を算出する
車の耐用年数、あるいは法定耐用年数は、基本的に「事業用」の車を対象とする計算方法で、減価償却の必要性から行われるものです。では具体的に、耐用年数はどのように算出されるのでしょう?
中古の普通自動車の耐用年数は、新車登録から6年が経過しているかがポイントになります。
6年以上であれば耐用年数は「法定耐用年数×0.2」で割り出されます。
6年未満であれば耐用年数は「法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2」で計算されます。
それぞれのパーツの寿命は?

以下では、特に細かい点検や交換が必要な部品について、その耐用年数とあわせて説明していきます。
タイミングベルトは「10万キロ」
タイミングベルトは、エンジンの性能に大きく影響するパーツで、10万キロを目安に交換するのが適当とされています。タイミングベルトが断裂するとエンジンが故障するので、交換・修理費用は高くつきます。走行距離が10万キロ未満でも断裂するケースがあるので、あまり走っていないからと言って油断はできません。
走行中にタイミングベルトが切れれば他の部分にも影響を及ぼして、最悪の場合「出火」することもあります。
タイミングベルトの特徴は、断裂するとエンジンを始めとする他の部品にも故障が発生するという点です。それらの修理費用を全て合わせると20万円を超すこともあるので、普段からメンテナンスが重要です。
また、金属製のタイミングチェーンを採用した車も近年増えてきています。タイミングチェーンは10万キロで交換の必要がなく、断裂の危険性も極めて少ないので中古車選びをする際にはタイミングチェーンを搭載した車で検討するのもいいでしょう。
バッテリーは「2~3年」
バッテリーは2~3年ごとに交換するのが一般的です。交換にかかる費用は決して高額ではないものの、工賃がおおむね2,000円程度なのに対し、バッテリー本体の価格はかなり幅があるため一概には言えません。
バッテリーも走行に欠かせないアイテムで、止まってしまうと電力供給がストップし、車は止まってしまいます。その一方で非常に消耗が激しく、車に長く乗りたいのであればこまめな点検や交換が欠かせません。
バッテリーは使えば使うほど劣化しますが、逆に全く使わなくても劣化が進むので注意が必要です。車を運転すること自体がバッテリーの寿命を延ばすことにつながるので、定期的にエンジンをかけて走行するようにしましょう。
タイヤは「4年前後」
タイヤについて、メーカーは4~5年を交換目安としていますが、これは素材や走行距離によって前後します。基本的には低燃費のタイヤの方が寿命は短めだと言える程度で、雪道や未舗装の道を走る機会があるかどうかでも変わってきます。
タイヤの溝は走るたびに摩耗しますが、すり減り具合を知らせてくれるのがスリップサインです。新品は溝が8mmですが、摩耗が進んで1.6mmになるとスリップサインが露出してくるので、1ヶ所でも露出が確認されたタイヤは早めに交換しましょう。
溝がないタイヤで走ると制動距離が長くなり、路面状況によってはスリップしやすくなるので大変危険です。また、そのまま放置していると車検も通りませんし、最悪の場合反則金の支払いや違反点数の累積を受けることもあります。
タイヤはゴムでできているので経年劣化は避けられません。ひび割れが発生すると、走行中にバーストする危険性もあります。
どんどん伸びている車の寿命
2019年3月の調査によると、軽自動車を除く乗用車の平均使用年数は、約13年という結果になっています。軽自動車の場合は約15年で、こちらは普通自動車よりも長く使われる傾向があります。このように自動車の寿命が延びているのは、自動車製造の技術や安全性の向上によるところが大きいでしょう。故障や事故が減少して、車も安定的に乗り続けられるようになっています。
かつて、乗用車は7年程度で買い替えるのが一般的でした。しかし、現在は10年以上乗っても、また10万キロ以上走行しても、状態によっては中古車として高額で買い取られることもありますし、その程度なら日本製の中古車は海外では普通に乗られています。
メンテナンスや部品の交換次第で10年でも20年でも乗れるのは頼もしい限りですが、どうなった時点で寿命と捉えるか、という問題もあります。人によっては修理費用が多くかかるようになったら寿命、と考えることもあるでしょう。
耐用年数が長くなっている
かつて、自動車は5年も乗ればボディはボロボロになり、さらに10万キロ走行したとなればエンジンが壊れて各種パーツもガタが来るのが当たり前でした。そうなると中古車としても価値はなく、廃車にするしかありません。しかし、今は技術力の向上によって、10年経っても美しい状態を保ち、安定的に走れる車が増えています。
走行距離が10万キロを超えても、こまめにメンテナンスを行えば中古車として高く売れる場合もあります。
海外で高く売れている
最近は、長期間あるいは長距離を走った車でも、中古車として高く売れることが多くあります。その理由の一つとして、日本の中古車が海外で好調に売れていることが挙げられます。通常、日本ではパワーウインドウやエアコンは最初から本体に付いていますが、海外ではそれらは標準装備ではありません。その分の付加価値が高くなるのに加えて、日本車はその燃費の良さと耐久性ゆえに評価が高いのです。
耐用年数が長く、オプション付きで燃費の良さは世界一とまで言われる日本車は、こうした理由から海外での需要が高まっています。
日本で新車登録された車の3分の1が海外に出ているほどで、最近は東南アジアにも販路が拡がっています。
車を長く乗り続ける場合の注意点
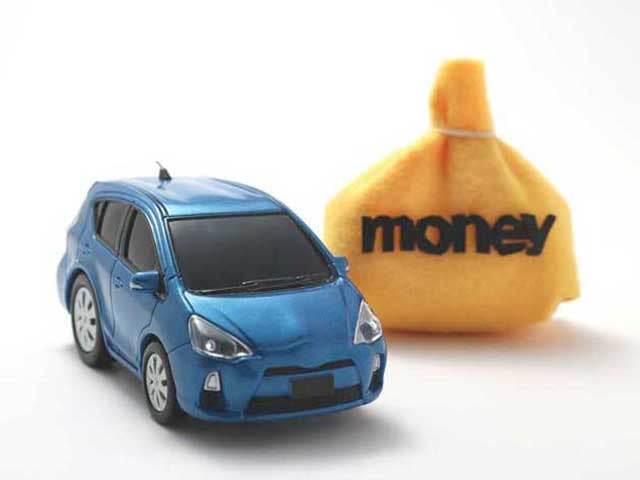
もちろん、長く乗ればそれだけ部品の劣化が進んで故障しやすくなりますし、定期的に部品交換や修理を行わなければなりません。
もっと長く乗るためには、具体的にどんな点に注意するべきなのでしょう?
売ってもほとんど値が付かないことがある
車は新車登録されてから一年ごとにその価値が下がっていき、5年で半分、10年ではほぼゼロになると言われています。経年劣化による価値の下落は、売却時の査定額に影響することになるでしょう。もしも海外に販売ルートを持っている買取業者であれば、古い車でも比較的高値で買い取ってもらえる可能性があります。
しかし、国内のみの販路しかない業者であれば、高値で売却することについてはあまり期待はできないかもしれません。
劣化により維持費は高くなる
どんな製品でも使えば使うほど劣化するもので、車の場合は部品の劣化や故障が増えるのにあわせて維持費も増すことになります。しかも、普通車の場合は新車登録から13年が経つと自動車税の税額もアップします。
また、10年以上が経った車でマイナーチェンジやフルモデルチェンジが行われていたりすると、純正の部品が入手しづらく部品代が高くつくこともあるでしょう。
古くなると燃費も悪くなり、全体的にお金がかかるようになります。
中古車購入は何年乗ったものが狙い目なのか

それは、車検のタイミングで車を売却する方が多く、車の種類や数が多いからです。
車検にあわせて手放された中古車が狙い目
高年式の車が欲しいなら、3年目の最初の車検を受けておらずなおかつ走行距離が短いものを探すのがおすすめです。ローンや残高設定型クレジットは支払期間が5年に設定されているケースが多いため、返済が終わったタイミングで売られた車もよくあります。
3年と5年という数字は、車のメーカー保証の期間とも重なります。一般保証が3年、特別保証が5年なので、この保証が切れるタイミングで車を買い替える方も多いです。
さらに、7年目あるいは9年目の車検のタイミングになると車を買い替える方はもっと増えるので、この年式の中古車は流通量も格段に多いです。
これらの年式を基準に中古車を探すと、安い良質なものを見つけやすくなるでしょう。
故障などのリスクも考えて購入する
中古車は新車と比べて故障のリスクが高く、その点は覚悟が必要です。もちろん10年が経った車だから故障ばかりするとは言い切れませんが、故障が起きても対処できるように準備はしておきましょう。
大切なのは、「走行距離」「年式」「整備状況のバランス」を考えて購入することです。
ただし、整備状況や安全性について素人が確認するのは難しいので、購入前に販売店側とよく話し合っておくことをおすすめします。
購入後の故障などのリスクをできるだけ避けるには、メンテナンスや修理、部品交換をこまめに行うことが大切です。
これらの注意点を念頭に置いておけば、10年落ちの車でも掘り出し物を見つけられるかもしれません。
まとめ
①車の寿命は「初回登録から10年」「走行距離10万キロ」とされている
②パーツについてはタイミングベルトが10万キロ、バッテリーは2~3年、タイヤは4年前後とさまざま
③今の車は耐用年数が長く、メンテナンス次第では20万キロ走ることも可能なので海外で高く売れている
④車を長く乗り続けると、売却時に値がつかない、劣化により維持費が高くつくなどのデメリットも
⑤中古車購入は車検直前に手放されたものが狙い目
この記事の画像を見る
