中古車購入チェックポイント
更新日:2022.02.28 / 掲載日:2022.02.28
中古車は何年乗ることができる?判断基準や注意すべき点などを説明!
中古車を選ぶ際、この車に何年ぐらい乗れるのだろう?と疑問に思うこともあるでしょう。
車は安く買って長く乗り続けられるのが理想ですが、そんな車に巡り合える可能性はとても低いです。そのため、車の寿命とライフプランを比較して考える必要があります。
車の寿命を判断する一般的な基準は「年式」と「走行距離」です。その両者のバランスも大切になるので説明していきます。
また、車を長く乗り続けた場合のメリットとデメリットについても紹介しますので参考にしてください。

こうした客観的な数字を目安にすれば、一つの車両について何年乗れるのかと計算することが可能です。
一方、車の持ち主の「何年乗りたい」という希望を目安にして、メンテナンスによってその年数もたせるという考え方もあります。
中古車の市場価値は一般的に10年でほぼゼロになります。実際にはメンテナンス次第で15年、20年、30年と乗ることもできますが、統計的には13年で車を手放す方が多いとされます。
結局、車の寿命はどこに基準を置くかによって、捉え方も異なるということです。そして、最も有力な基準となるのが「年式」と「走行距離」の2つです。
以下では、この2つについて詳しく説明していきます。

年式は車の年齢のことで、その車が新車登録されてから何年が経ったかを表す数字です。
車は、年数が経過すれば劣化が進んでいきます。この劣化の度合いは車の扱い方によって大きく異なります。
そのため、中古車の年式は車両の状態を見極めるための大きな基準となります。
登録年が昔であればあるほど、その車の年式は古いことになります。ただし、製造年と登録年がずれることもあるので、年式の数字はあくまでもおおよその目安です。
因みに、海外で販売されている車を日本の販売店が独自に輸入したものは、大まかな製造年にあたる「モデル年式」が採用されます。
年式は「高年式」「低年式」という言葉で表現されることもあります。
高年式は、一般的に製造・登録されてから約3年以内の車のことを指します。比較的新車に近い年式のため長く乗り続けれらることが多いです。
低年式は、製造・登録されてから約7年以上経ったものを指しますが、特に厳密な定義はありません。
また、年式と似た言葉で「○年落ち」という言い方がされることもあります。
まず、10年経つとタイミングベルトやエンジン周りの機器が劣化します。
また、10年経った純正部品はメーカー側の保存義務がなくなるので修理・交換が難しくなることなどがあります。
それらと相関して、中古車市場でも10年経った車はほぼ無価値となるでしょう。
ただし、実際には乗用車の平均使用年数は約13年と言われていますし、最近の車は性能がいいので、メンテナンスをきちんとしていれば10年以上乗るのは難しくありません。
なぜ平均使用年数が13年なのかというと、税金に一つの理由があります。新規登録から13年以上経った車は自動車税・自動車重量税が上がります。(一部のエコカーなどを除く)
自動車税は、車の維持費の中でも車検代に次いで負担が大きい部類です。そのため、税額が増える前に売却する人が増えるのであって、必ずしも車の寿命が13年ということを意味するわけではありません。
大切なのは車を乱暴に扱わないこと、定期的にメンテナンスすること、部品交換のタイミングを押さえておくことです。
特にエンジンのメンテナンスが重要で、故障して交換すると約50万円はかかります。ちょっとした中古車が買える金額となるので、そうならないようエンジン周りはこまめにメンテナンスを行いましょう。
また、エンジンオイルとオイルフィルターも定期的に交換してください。放置するとエンジンの故障につながるので、決められた走行距離あるいはタイミングに達したら必ずお店で交換してもらいましょう。
その他、バッテリー、燃料ポンプ、タイヤなど細かい部品の点検や交換は専門家に任せて大丈夫です。
最近は自動車メーカーの技術も進化しており、こうした点検や交換をこまめに行えば、車に10~20年乗るのも決して不可能ではありません。

車の走行距離はメーターで確認することができますが、この数値もまた車の状態を推し量る重要な手がかりとなります。
たとえ新車で購入した車でも、普通は10万~15万キロ以上乗れば車両はかなり劣化し、寿命も縮んでいると見なされます。
走行距離が長くとも、こまめなメンテナンスや部品交換を行えば乗り続けることは可能です。しかし、それは延命措置であって長く乗れば乗るほど結局費用や手間などのコストはかさむことになります。
タイミングベルト、ウォーターポンプ、クラッチなども10万キロが交換の目安とされています。
なぜ10万キロが寿命なのかというと、車の平均的な走行距離は1年で1万キロと言われているからです。よって10万キロ走れば、単純計算で車の寿命は10年という時期に達することになります。
10万キロに達したら、もうその車に乗れないというわけではありません。しかし、10年が経過した車両と同様にメンテナンスや部品交換をこまめに行わないと劣化が早く進むのは間違いないでしょう。
かと言って走行距離が短ければ長持ちするというわけではなく、むしろ放置することでかえって車両の状態が悪化することもあります。
大切なのは適度に走行しながら適切にメンテナンスを行っていくことです。
しかし、メンテナンス次第でもっと長く乗れることも珍しくありません。
日本製の中古車は、海外でも高い人気を誇っています。その大きな理由の一つが耐久性にあります。
例えばトヨタのハイエースなどは、メンテナンスをこまめに行って20~30万キロまで乗り、廃車になるまで使い尽くされるケースも多いです。
走行距離だけで単純に車の価値を判断することはできないので、年式や車のコンディションなどのバランスを見るようにしましょう。
10万キロや10年というのは、あくまでも分かりやすい指標の一つです。ただし、長く乗ると維持費がどうしても問題になります。
10万キロあるいは10年超えの中古車の維持費はかさみがちで、トータルで考えると買い替えたほうが安く済むこともあります。
では、年式と走行距離がどれくらいのバランスだといいのかというと、一般的によく言われる「1年で1万キロ」くらいの範囲が適切なラインだと言えます。
どんなに新しい年式の車両でも走行距離が平均以上であれば、車体や部品に余計な負荷がかかって劣化している恐れがあります。そのような場合、購入直後から部品交換などメンテナンスの必要が生じるかもしれません。
逆に、年式が古いのに走行距離が短い場合も要注意です。長期間ほとんど運転されておらず放置された状態で満足な管理が行われていない車だったりすると、本格的に運転し始めた途端にあちこちで不具合が発生することもあります。
この内容を踏まえた上で、以下では中古車に何年乗れるのかを考えてみます。
年式や走行距離という一般的な基準を踏まえつつ、「自分は車に後何年乗りたいか」「所有する車に後何年乗れるか」という問いに答える形で考えてみましょう。
この場合もいくつかのパターンがあるので、ケースごとに説明していきます。
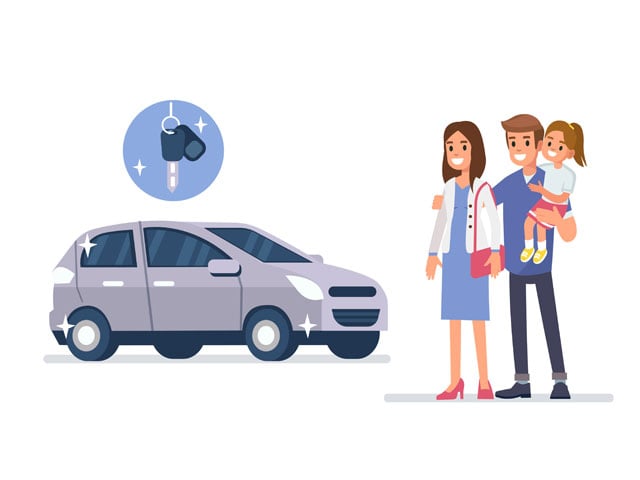
希望する期間については以下の3パターンが考えられます。
・ごく短期間だけでいい場合
・状況に合わせて乗り換える場合
・ずっと乗り続けたい場合
以下では、それぞれの状況にあわせた中古車の選び方について説明します。
車が必要な期間がもっと短いのであれば、「レンタカー」や「カーリース」の利用も検討してみてもいいかもしれません。使用するのが3~4ヶ月程度であればレンタカーのほうがお得で、それを超える場合はカーリースのほうがお得とされています。
基本的には、1台の車を乗り潰したほうが車両代金は安く抑えられます。しかし、例えばライフスタイルが変わったことで走行距離が長くなるなら、燃費が抑えられる「ハイブリッドカー」や「クリーンディーゼル車」を選んだほうが良いでしょう。
また、子供の誕生、入学、就職、引っ越しなどの時期は、車の乗り換えを検討すべきタイミングです。家族みんなで乗れる「ミニバン」を選んだり、子供の独り立ちに合わせて「一回り小さい車」にしたりするなどの選択肢が考えられます。
ただし、20~30年乗るためには日常的・定期的な点検やメンテナンス、部品交換が必須です。その費用と手間を考えると、結局買い替えたほうがコストがかからずに済むとも言えます。
チェックポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。
・最も破損しやすいタイミングベルト
・ボディの下回りのサビ
・試乗した時にほんの少しでも違和感がないか
また、整備記録簿によってきちんとメンテナンスが行われていたかどうかも確かめてください。整備記録簿には、それまでの不具合や部品交換の履歴が全て記載されています。
乗用車は、新車・中古車にかかわらず購入する時に最もお金がかかります。
トラブルなく長期間乗り続けられれば、どこかの時点で買い替えのために必要になったかもしれない費用分が長期間で分割できることになり、経済的な負担が減ります。
また、車を長く所有すれば愛着が湧く点も大きなメリットです。
まず、故障や不具合のリスクが高くなりますし、そのための費用と手間がかかることです。
車両の維持費は主に燃料費、メンテナンス費用、税金などです。低年式の車ほど燃費が悪くなり、さらに修理や整備が必要になることも多くなります。その上、税金も高くなるので、総じてコストがかかると言えるでしょう。
また、中古車市場での車の価値は新車登録時から数えて5年で3〜4割になり、10年でほぼゼロになると言われています。
年数が経つごとに売却時の査定額も減少していくので、低年式の中古車は売却時に値が付きにくいのもデメリットです。
車を売却する際は、海外への販売ルートを保有している業者や廃車にして廃車専門の業者に持ち込んだほうが高く売れることもあります。国内販売のルートしか持たない業者は、高値での売却はあまり期待できません。

購入する車の寿命を推し量り、そこから「あと何年くらい乗れそう」と考える方のほうが多いかもしれません。
以下では、車両の状態から寿命を推し量り、そこから「何年乗るか」という結論を導き出す場合の2つのパターンについて説明します。
寿命よりも「どんな車が欲しいか」を優先して考えているケースです。
2019年に行われた調査によると車の平均使用年数は13.26年と言われているので、一例としてこの数字から年式の数値をマイナスすれば「あと何年乗れるか」の目安が算出できます。
また、少なくとも13年は乗るという目標値を先に定めておくのも一つの手です。
後は、こうして導き出した予定使用年数が、走行距離と釣り合いが取れているかも確認してください。
注意点は、こうした高品質の車は割高だということです。新車と大差ない価格だった場合は、車種によほどのこだわりがなければ中古ではなく新車でもいいでしょう。
一方、高年式・低走行車で割安のものは、性能面や安全面でどこかに不安な点があることが考えられます。大規模な修復歴や水没した履歴があると故障しやすいので、整備記録簿を綿密にチェックし、販売店スタッフにもきちんと確認することが必要です。
車は安く買って長く乗り続けられるのが理想ですが、そんな車に巡り合える可能性はとても低いです。そのため、車の寿命とライフプランを比較して考える必要があります。
車の寿命を判断する一般的な基準は「年式」と「走行距離」です。その両者のバランスも大切になるので説明していきます。
また、車を長く乗り続けた場合のメリットとデメリットについても紹介しますので参考にしてください。
この記事の目次
中古車は何年乗り続けられる?

こうした客観的な数字を目安にすれば、一つの車両について何年乗れるのかと計算することが可能です。
一方、車の持ち主の「何年乗りたい」という希望を目安にして、メンテナンスによってその年数もたせるという考え方もあります。
車の寿命が後何年かを確認しておこう
車の寿命の見方は様々です。中古車の市場価値は一般的に10年でほぼゼロになります。実際にはメンテナンス次第で15年、20年、30年と乗ることもできますが、統計的には13年で車を手放す方が多いとされます。
結局、車の寿命はどこに基準を置くかによって、捉え方も異なるということです。そして、最も有力な基準となるのが「年式」と「走行距離」の2つです。
以下では、この2つについて詳しく説明していきます。
年式を基準にした場合

年式は車の年齢のことで、その車が新車登録されてから何年が経ったかを表す数字です。
車は、年数が経過すれば劣化が進んでいきます。この劣化の度合いは車の扱い方によって大きく異なります。
そのため、中古車の年式は車両の状態を見極めるための大きな基準となります。
年式とは?
車の年式とは、車が製造され運輸支局に新車として初めて登録された初度登録年(軽自動車の場合は初度検査年)のことを指します。登録年が昔であればあるほど、その車の年式は古いことになります。ただし、製造年と登録年がずれることもあるので、年式の数字はあくまでもおおよその目安です。
因みに、海外で販売されている車を日本の販売店が独自に輸入したものは、大まかな製造年にあたる「モデル年式」が採用されます。
年式は「高年式」「低年式」という言葉で表現されることもあります。
高年式は、一般的に製造・登録されてから約3年以内の車のことを指します。比較的新車に近い年式のため長く乗り続けれらることが多いです。
低年式は、製造・登録されてから約7年以上経ったものを指しますが、特に厳密な定義はありません。
また、年式と似た言葉で「○年落ち」という言い方がされることもあります。
車の一般的な寿命は10年
車の寿命は様々な理由から10年と言われています。まず、10年経つとタイミングベルトやエンジン周りの機器が劣化します。
また、10年経った純正部品はメーカー側の保存義務がなくなるので修理・交換が難しくなることなどがあります。
それらと相関して、中古車市場でも10年経った車はほぼ無価値となるでしょう。
ただし、実際には乗用車の平均使用年数は約13年と言われていますし、最近の車は性能がいいので、メンテナンスをきちんとしていれば10年以上乗るのは難しくありません。
なぜ平均使用年数が13年なのかというと、税金に一つの理由があります。新規登録から13年以上経った車は自動車税・自動車重量税が上がります。(一部のエコカーなどを除く)
自動車税は、車の維持費の中でも車検代に次いで負担が大きい部類です。そのため、税額が増える前に売却する人が増えるのであって、必ずしも車の寿命が13年ということを意味するわけではありません。
実際には10~20年乗れることも多い
多くの場合、車の寿命は10年と言われますが、もっと長く乗り続けることも可能です。大切なのは車を乱暴に扱わないこと、定期的にメンテナンスすること、部品交換のタイミングを押さえておくことです。
特にエンジンのメンテナンスが重要で、故障して交換すると約50万円はかかります。ちょっとした中古車が買える金額となるので、そうならないようエンジン周りはこまめにメンテナンスを行いましょう。
また、エンジンオイルとオイルフィルターも定期的に交換してください。放置するとエンジンの故障につながるので、決められた走行距離あるいはタイミングに達したら必ずお店で交換してもらいましょう。
その他、バッテリー、燃料ポンプ、タイヤなど細かい部品の点検や交換は専門家に任せて大丈夫です。
最近は自動車メーカーの技術も進化しており、こうした点検や交換をこまめに行えば、車に10~20年乗るのも決して不可能ではありません。
走行距離を基準にした場合

車の走行距離はメーターで確認することができますが、この数値もまた車の状態を推し量る重要な手がかりとなります。
走行距離がなぜ基準になるの?
まず、走行距離がなぜ車の寿命を測る基準になるのかというと、車は走行するほど劣化してしまうからです。たとえ新車で購入した車でも、普通は10万~15万キロ以上乗れば車両はかなり劣化し、寿命も縮んでいると見なされます。
走行距離が長くとも、こまめなメンテナンスや部品交換を行えば乗り続けることは可能です。しかし、それは延命措置であって長く乗れば乗るほど結局費用や手間などのコストはかさむことになります。
車の一般的な走行距離の限界は10万キロ
車の走行距離の限界は10万キロというのが一般的で、実際その数値を超えたあたりから車両にトラブルが発生する頻度も高くなります。タイミングベルト、ウォーターポンプ、クラッチなども10万キロが交換の目安とされています。
なぜ10万キロが寿命なのかというと、車の平均的な走行距離は1年で1万キロと言われているからです。よって10万キロ走れば、単純計算で車の寿命は10年という時期に達することになります。
10万キロに達したら、もうその車に乗れないというわけではありません。しかし、10年が経過した車両と同様にメンテナンスや部品交換をこまめに行わないと劣化が早く進むのは間違いないでしょう。
かと言って走行距離が短ければ長持ちするというわけではなく、むしろ放置することでかえって車両の状態が悪化することもあります。
大切なのは適度に走行しながら適切にメンテナンスを行っていくことです。
実際には10~30万キロ乗れることもある
車は走行距離10万キロが一般的な寿命と言われ、それを超えると故障のリスクが高まるのは間違いないでしょう。しかし、メンテナンス次第でもっと長く乗れることも珍しくありません。
日本製の中古車は、海外でも高い人気を誇っています。その大きな理由の一つが耐久性にあります。
例えばトヨタのハイエースなどは、メンテナンスをこまめに行って20~30万キロまで乗り、廃車になるまで使い尽くされるケースも多いです。
走行距離だけで単純に車の価値を判断することはできないので、年式や車のコンディションなどのバランスを見るようにしましょう。
10万キロや10年というのは、あくまでも分かりやすい指標の一つです。ただし、長く乗ると維持費がどうしても問題になります。
10万キロあるいは10年超えの中古車の維持費はかさみがちで、トータルで考えると買い替えたほうが安く済むこともあります。
中古車は年式と走行距離のバランスが大事
中古車を選ぶ時はあくまでも年式と走行距離のバランスが大切です。どちらかに偏りがある場合は慎重な姿勢で臨むようにしましょう。では、年式と走行距離がどれくらいのバランスだといいのかというと、一般的によく言われる「1年で1万キロ」くらいの範囲が適切なラインだと言えます。
どんなに新しい年式の車両でも走行距離が平均以上であれば、車体や部品に余計な負荷がかかって劣化している恐れがあります。そのような場合、購入直後から部品交換などメンテナンスの必要が生じるかもしれません。
逆に、年式が古いのに走行距離が短い場合も要注意です。長期間ほとんど運転されておらず放置された状態で満足な管理が行われていない車だったりすると、本格的に運転し始めた途端にあちこちで不具合が発生することもあります。
中古車に何年乗り続けられるか考えてみよう
ここまでで、中古車の寿命を判断するのに最も有力な基準である年式や走行距離について説明してきました。この内容を踏まえた上で、以下では中古車に何年乗れるのかを考えてみます。
年式や走行距離という一般的な基準を踏まえつつ、「自分は車に後何年乗りたいか」「所有する車に後何年乗れるか」という問いに答える形で考えてみましょう。
この場合もいくつかのパターンがあるので、ケースごとに説明していきます。
「自分は車に後何年乗りたいか」を基準にする
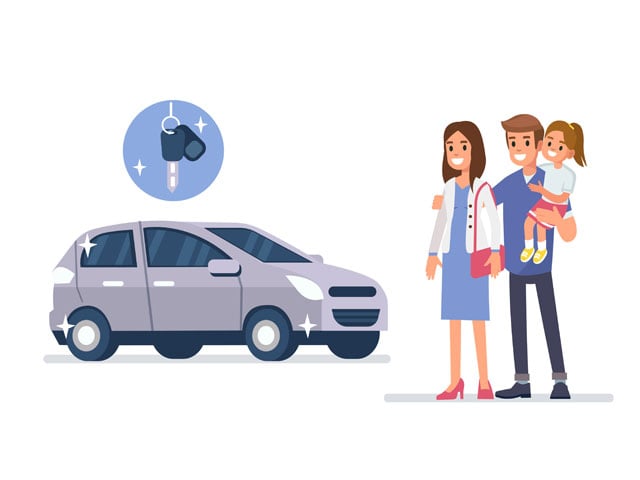
希望する期間については以下の3パターンが考えられます。
・ごく短期間だけでいい場合
・状況に合わせて乗り換える場合
・ずっと乗り続けたい場合
以下では、それぞれの状況にあわせた中古車の選び方について説明します。
①ごく短期間乗れればいいという場合
例えば、単身赴任などで数年間だけ赴任先で使う車が欲しい場合。短期間だけ車に乗りたいという方は、市場でも大きく値下がりし、初期費用も少なく済む「10年落ちの中古車」がいいでしょう。車が必要な期間がもっと短いのであれば、「レンタカー」や「カーリース」の利用も検討してみてもいいかもしれません。使用するのが3~4ヶ月程度であればレンタカーのほうがお得で、それを超える場合はカーリースのほうがお得とされています。
②ライフイベントに合わせて乗り換えたい場合
例えば、生活環境や家族の人数によって車をこまめに買い替えたいという場合。特に子供がいると乗車人数、荷物の積載量などに変化が生じ、適した車をその都度買い替えたほうがいいこともあります。基本的には、1台の車を乗り潰したほうが車両代金は安く抑えられます。しかし、例えばライフスタイルが変わったことで走行距離が長くなるなら、燃費が抑えられる「ハイブリッドカー」や「クリーンディーゼル車」を選んだほうが良いでしょう。
また、子供の誕生、入学、就職、引っ越しなどの時期は、車の乗り換えを検討すべきタイミングです。家族みんなで乗れる「ミニバン」を選んだり、子供の独り立ちに合わせて「一回り小さい車」にしたりするなどの選択肢が考えられます。
③長く乗れるだけ乗りたい場合
とにかく車を長持ちさせて長期間乗りたいという方は「日本車」を選びましょう。耐久性が高いので、20~30年乗るのも不可能ではありません。ただし、20~30年乗るためには日常的・定期的な点検やメンテナンス、部品交換が必須です。その費用と手間を考えると、結局買い替えたほうがコストがかからずに済むとも言えます。
長く乗れる中古車を見つける方法
状態が良好な車ほど長持ちするものなので、長く乗れる中古車を探すなら、まずは各種パーツの状態を確認しましょう。チェックポイントとしては主に以下の3つが挙げられます。
・最も破損しやすいタイミングベルト
・ボディの下回りのサビ
・試乗した時にほんの少しでも違和感がないか
また、整備記録簿によってきちんとメンテナンスが行われていたかどうかも確かめてください。整備記録簿には、それまでの不具合や部品交換の履歴が全て記載されています。
長く乗るメリット
車を長く所有することの最大のメリットは、買い替える費用がかからないという点でしょう。乗用車は、新車・中古車にかかわらず購入する時に最もお金がかかります。
トラブルなく長期間乗り続けられれば、どこかの時点で買い替えのために必要になったかもしれない費用分が長期間で分割できることになり、経済的な負担が減ります。
また、車を長く所有すれば愛着が湧く点も大きなメリットです。
長く乗るデメリット
中古車に長く乗り続けるデメリットもあります。まず、故障や不具合のリスクが高くなりますし、そのための費用と手間がかかることです。
車両の維持費は主に燃料費、メンテナンス費用、税金などです。低年式の車ほど燃費が悪くなり、さらに修理や整備が必要になることも多くなります。その上、税金も高くなるので、総じてコストがかかると言えるでしょう。
また、中古車市場での車の価値は新車登録時から数えて5年で3〜4割になり、10年でほぼゼロになると言われています。
年数が経つごとに売却時の査定額も減少していくので、低年式の中古車は売却時に値が付きにくいのもデメリットです。
車を売却する際は、海外への販売ルートを保有している業者や廃車にして廃車専門の業者に持ち込んだほうが高く売れることもあります。国内販売のルートしか持たない業者は、高値での売却はあまり期待できません。
「所有する車に後何年乗れるか」を基準にする

購入する車の寿命を推し量り、そこから「あと何年くらい乗れそう」と考える方のほうが多いかもしれません。
以下では、車両の状態から寿命を推し量り、そこから「何年乗るか」という結論を導き出す場合の2つのパターンについて説明します。
寿命よりも「どんな車が欲しいか」を優先して考えているケースです。
①乗りたい車が決まっている場合
乗りたい車種が既に決まっており、希望の条件に該当する車を見つけたなら、まず年式を確認しましょう。2019年に行われた調査によると車の平均使用年数は13.26年と言われているので、一例としてこの数字から年式の数値をマイナスすれば「あと何年乗れるか」の目安が算出できます。
また、少なくとも13年は乗るという目標値を先に定めておくのも一つの手です。
後は、こうして導き出した予定使用年数が、走行距離と釣り合いが取れているかも確認してください。
②とにかく高年式で走行距離が短いものを選ぶ場合
とにかく高年式・低走行車が欲しいという方もいるでしょう。言い換えれば「新品に近く、できるだけ安価なものが欲しい」ということで、このような中古車が手に入れば、新車同様に長く乗り続けられます。注意点は、こうした高品質の車は割高だということです。新車と大差ない価格だった場合は、車種によほどのこだわりがなければ中古ではなく新車でもいいでしょう。
一方、高年式・低走行車で割安のものは、性能面や安全面でどこかに不安な点があることが考えられます。大規模な修復歴や水没した履歴があると故障しやすいので、整備記録簿を綿密にチェックし、販売店スタッフにもきちんと確認することが必要です。
まとめ
①年式を基準にすると、車の一般的な寿命は10年とされる
②走行距離を基準にすると、車の一般的な走行距離の限界は10万キロとされる
③実際には10年以上、10万キロ以上乗れることもある
④ただし、長く乗ることにはメリットとデメリットがある
⑤中古車は「年式」「走行距離」のバランスが大事
⑥中古車は自分が何年乗りたいのかを基準にして選ぶといい
⑦欲しい中古車の状態から、あと何年乗るかを決めてもいい
この記事の画像を見る
