中古車購入チェックポイント
更新日:2024.06.24 / 掲載日:2022.05.31
中古車の耐用年数の算出方法とは?計算方法や注意点について解説
新車と違い中古車の耐用年数は計算式があり、それをもって算出します。計算式を知っておけば、減価償却をする時に役立つでしょう。
車は固定資産です。減価償却するためには耐用年数が重要になってきますので、経費計上するときに必須です。
この記事では、中古車の耐用年数の算出方法と注意点について詳しく解説していきます。

耐用年数とは?
一般的に事業に使う資産について長期間使用する際は「固定資産」に分けられます。耐用年数とは、資産として使用可能できる期間のことです。これは、国税庁が定めている固定資産の法定耐用年数を使用します。車だけではなく、不動産や備品について金額が高価になるものは、このケースが当てはまります。
実際のところ、経理処理のために必要です。つまり、新規に購入した資産価値を基準にして、資産の種類や構造によって詳細が決められています。
固定資産になるものに関しては、取得時に一括で経費として計上することができず、耐用年数に応じて減価償却をすることが背景としてあります。そのため、中古資産を購入した場合には、経過年数をもとに所定の計算式で算出し、耐用年数を決定させます。
中古資産は使用状況や劣化などで耐用年数が左右されず、変動することはないという点は覚えておきましょう。
購入状況によって車の耐用年数は変化する
車を事業用で購入した場合、新車と中古車では耐用年数が異なってきます。それは、車の経過年数に応じて変化するからです。耐用年数の考え方は「使用可能期間がどの時期まであるのか」が基準になります。そのため、個々の車の状況に応じて異なってくることが考えられます。
固定資産は取得時期から何年使えるかがポイントになりますので、自動車の場合は種類、大きさ、使用用途に応じて変化していきます。それは、税の公平性を保つために必要なことと言えるでしょう。
新車購入の場合
耐用年数は、国税庁で詳細が定められています。新車の場合の耐用年数は、以下の通りです。<一般用>
・普通自動車:6年
・軽自動車:4年
・貨物自動車:ダンプ式は4年・その他は5年
・自転車:2年
<運送事業用>
・乗合自動車:5年
・小型車(貨物自動車で積載量2t以下、その他排気量が2L以下):3年
・大型乗用車(総排気量が3L以上):5年
使用用途によっても耐用年数が変わりますので、注意しましょう。
中古車購入の場合
中古車は以前のオーナーが使用していた車なので、使用頻度やコンディションも異なります。正確に使用可能期間を決定することは難しいでしょう。そのため、新規登録をした時期から月数を確認して耐用年数を決定します。これからお伝えする計算式から算出した年数を耐用年数として使用することが可能です。
また、中古車の場合には30万円をボーダーに減価償却について考え方が変わります。
30万円未満の中古車については一括で費用計上ができます。これは、少額減価償却資産として扱うことができるからです。つまり、購入した事業年度にそのまま経費計上することができます。
それに対して、30万円以上の中古車は、耐用年数から償却することになります。
中古車における耐用年数の計算方法

税制として公平性を保つためにも、必要なことと言えます。そのため、中古車は使用状況によっても個々で程度は異なりますが、一般的な耐用年数を定めることが求められているので、簡便法を用いています。
計算式に関しては、以下の通りです。
中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)
ただし、1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年以内になる場合は、耐用年数は2年になります。
具体例を挙げて計算してみます。
4年落ちの中古車(普通自動車)のケースは以下のようになります。
(6年(法定耐用年数)ー4年(経過年数))+(4年(経過年数)×0.2)=2年+0.8年=2.8年
1年未満の端数は切り捨てなので、4年落ちの車の耐用年数は2年になります。
また、中古車の法定耐用年数を越えているケースでは以下の計算式になります。
中古車の耐用年数=法定耐用年数×0.2
具体例を挙げて計算してみます。
経過年数が7年の普通自動車の場合、法定耐用年数は6年になりますので、以下のようになります。
6年(法定耐用年数)×0.2=1.2年
計算結果が2年以内の場合は耐用年数は2年なので、この場合は2年になります。つまり、経過年数が法定耐用年数を越える場合は2年です。
経過年数による耐用年数一覧
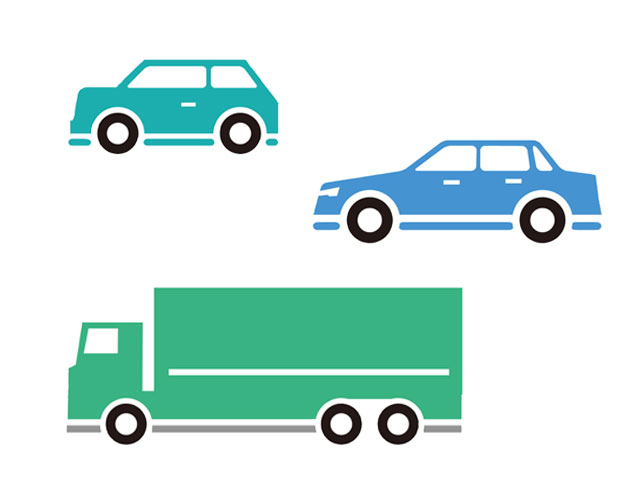
減価償却に視点を向けると、耐用年数が短くなればなるほど経費として計上できる金額も多くすることが可能です。そのため、早期に減価償却を行いたい場合には、中古車のメリットが活用できるでしょう。
時期をみながら事業用の中古車を購入することも視野に入れておくのが良いかもしれません。
軽自動車や普通乗用車について、経過月数による耐用年数をまとめてみました。車がどの時期であればどの耐用年数にあるのか、確認してみてください。
軽自動車
軽自動車の新車による法定耐用年数は4年です。中古車における耐用年数の推移は次の通りです。<新車登録からの経過月数:対応年数>
・1ヶ月~15ヶ月:3年
・16ヶ月以上:2年
例えば、16ヶ月経過していると計算式は(4-1.33)+(1.33×0.2)=2.67+0.266=2.936になります。1年未満は切り捨てになりますので、耐用年数は2年になります。
もし、早期の経費計上を検討している時には、新規登録から16ヶ月(1年4ヶ月)が経過している軽自動車がおすすめです。
普通自動車
普通自動車は法定耐用年数は6年です。中古車における耐用年数の推移は次の通りです。<新車登録からの経過年月数:対応年数>
・1ヶ月~15ヶ月:5年
・16ヶ月~30ヶ月:4年
・31ヶ月~45ヶ月:3年
・46ヶ月以上:2年
例えば、46ヶ月(3.83年)経過していると計算式は(6-3.83)+(3.83×0.2)=2.936になります。1年未満は切り捨てですので、耐用年数が2年になります。
普通自動車であれば、新規登録してから3年後に車検がありますので、中古車市場に出回る時期でもあります。ワンオーナーで乗っているケースが多いので、程度の良い車を手に入れられる可能性が高いと言えます。
それ以外であれば、2回目の車検になる5年前後だと耐用年数が2年なので、早期に減価償却も可能になります。
貨物自動車の法定耐用年数
今まで、軽自動車と普通車を中心に解説してきましたが、貨物自動車についても国税庁が定める法定耐用年数があります。以下では、主な減価償却資産の耐用年数を記載しておきます。
・一般用のダンプ式貨物自動車:4年
・その他貨物自動車:5年
・運送事業といった業務用の2トン以下の貨物トラック:3年
・総排気量3リットル以上の大型トラック:5年
・その他のトラック:4年
一般的に業務用車は使用頻度が高い傾向があるため、耐用年数が短くなるケースが多いです。
貨物自動車は整備点検等の頻度が多くなるため、その経費も考慮に入れておくと良いでしょう。
貨物自動車の車検の有効期限は、事業用で車両総重量8t未満であれば、初回が2年で2回目以降は1年、車両総重量が8t以上であれば一律で1年になっています。また、事業用の軽自動車の場合は一律で2年です。
一般的な事業用貨物自動車の車検は、軽自動車を除き基本的に1年であることを覚えておきましょう。
短期間で減価償却したい時の耐用年数

中古車の場合は新車と違い、前オーナーの使用状況によって異なります。そのため、経過月数も含めて程度の良い中古車を選ぶことが大切です。
一般的に狙い目の経過月数として、軽自動車なら16ヶ月、普通乗用車であれば16ヶ月・31ヶ月・46ヶ月です。この時期は、耐用年数が引き下がる分岐点になるため、減価償却時に計上できる金額が多くできます。
また、車の平均使用年数は年々長くなっています。一般財団法人自動車検査登録情報協会が発表している平成31年3月末の平均使用年数は、「普通乗用車が13.26年」「貨物車が15.17年」です。これは、車の性能向上が起因していると言えます。
現状、しっかり整備されている車であれば、耐用年数に関係なく使用できる可能性が高いです。車のコンディションも確認した上で、税金面も考慮に入れたバランスの良い車の購入を心がけましょう。
減価償却する際の注意すべき点

固定資産の減価償却は耐用年数ばかりではなく、その他の項目を知っておくことで、より節税対策にも繋がります。
ここからは、注意すべき3つのポイントについて詳しく解説していきます。
①取得日に注意
ポイントの1つ目として、取得日があります。時期によっては、計上できる金額が異なりますので注意が必要です。理由として減価償却は、年単位ではなく、月数按分で行われるからです。つまり、取得日が事業年度の初月ならば全てを経費として計上可能ですが、年度途中に購入すると事業年度中の残り月数のみ計上することになります。
そのため、事業年度と取得日を関連付けさせることが節税対策には大切です。ちなみに取得日は納車される日を指します。
実際に減価償却をするための計算式は以下の通りです。
取得価額×償却率×事業年度内で使用した月数÷12
もし、事業年度最終月に中古車を購入した場合は、1ヶ月分のみの経費計上になってしまいます。残りの11ヶ月分は次年度の経費として計上されてしまいますので気をつけましょう。
中古車を事業車として購入する時には、事業年度初めがおすすめです。
②資本的支出が再取得価額の50%を超える中古車
ポイントの2つ目が、資本的支出が再取得価額の50%を超えるケースです。再取得価額とは、中古資産と同一の資産を新品で購入した場合の価額のことです。
国税庁では、資本的支出の金額が中古資産の再取得価額の50%を超える場合は、法定耐用年数を適用することとしています。ここで言われている「資本的支出」とは、単なる修繕的なものではなく、「その資産に対して、新たな価値を加えたり、使用可能期間が延長されるような価値を高める支出」のことを指します。
つまり、中古車を購入後、車の価値を高め、使用可能期間が延長できるように高性能のエンジンを乗せ換えたりするのに発生した費用が資本的支出にあたります。
例えば、同一の新車価格が200万円で実際の購入価格が100万円の中古車であるケースでは、4年落ちの普通乗用車の耐用年数は2年です。しかし、資本的支出が120万円かかった場合は、再取得価額が50%(100万円)を超えているので、法定耐用年数の6年が適用されることになります。
一方、資本的支出が中古資産の取得価額(購入額)の50%を超えている場合は、特別な計算方法で耐用年数を算出することになります。
例えば、中古の3年落ち普通自動車の取得価額(購入額)が100万円で、資本的支出が60万円の場合は、取得価額が50%を超えているので、特別な計算方法を使用することになります。計算式は以下の通りです。
(中古資産の価額+資本的支出の額)÷(中古資産の価額/簡便法の耐用年数+資本的支出の額/法定耐用年数)
(100万円+60万円)÷(100万円/3年+60万円/6年)=3.69年
※簡便法の耐用年数( 72ヶ月 – 36ヶ月 ) + 36ヶ月 × 20% = 3.6年
1年未満は切り捨てになりますので耐用年数は「3年」になります。
このように、資本的支出がある場合は、再取得価額が50%を超える時と、取得価額が50%を超える際には、耐用年数が簡便法で対応できないケースがあることを知っておくと良いでしょう。
③取得価額に含む費用
固定資産の取得価額については、法律上で定められる「含める費用」と「含めなくて良い費用」があります。含めなくて良い費用については、他の勘定科目で仕分けできる項目もあります。そのため、実際に仕分けで困らないようにしておくと安心です。
中古車購入時に取得価額に関係がある費用は以下の通りです。
<含める費用>
・車両本体価格
・オプション費用
・納車費用
<含めなくても良い費用>
・自動車重量税
・自賠責保険料
・自動車税種別割
・自動車環境性能割
・車庫証明
・検査登録(車検)費用
基本的に車本体にかかる費用については、取得価額に必ず含む必要がありますので、忘れずに行いましょう。
また、従業員500名以下の中小企業は特例があります。令和4年3月31日までに減価償却資産で30万円未満のものを取得した時は、年間300万円を限度額として、全額経費計上できることになっています。
これが「少額減価償却資産の特例」です。この特例は2年ごとに延長されることになっており、令和4年度の税制改正大綱で適用期限がさらに2年間延長されています。
車を購入した後に30万円未満のカーナビなどの備品を購入する時は、車と一緒に購入するよりも後で取り付けることで、一括償却することが可能です。オプション等については、後付け可能であれば節税対策に繋がりますので、活用すると良いでしょう。
ただし、車の項目ではあまり影響はありませんが、今回の改正で「貸付けの用に供した資産」を除くことが決まっているので、注意してください。
中古車購入は何年落ちがお得なのか

一般的に中古車を購入すると良いとされているのは、3年・5年・7年落ちと言われています。その背景に大きく関わっているのが「車検」です。
新車を購入して最初の車検が3年ですので、次の車検まで乗り続けるか、売却するかを所有者は考えることになります。乗り換え時期が車検前のことが多いのはそのためです。
そういった理由もあり、市場に出回りやすい中古車は3年・5年・7年落ちが多いです。
しかし、事業用であれば、購入時期と経過年数で経費を抑えることを考えるので、時期が重要になります。
普通自動車であれば、事業年度の初月に購入する、経過年数は3年10ヶ月が減価償却を多く費用計上することが可能です。
なかなか、経過年数がピッタリとはいかないこともあるかもしれませんが、探してみる価値はあります。
メリットを最大限活かすためにも、妥協せずに中古車販売店のサイトを検索してみると良いでしょう。
事前に販売店の担当者にも依頼をしておき、条件に適合する中古車がある場合には連絡してもらうことがおすすめです。
まとめ
①新車の法定耐用年数は、「普通自動車が6年」「軽自動車が4年」になっている
②中古車を購入した場合、経過年数に応じて耐用年数が異なり、年数算出は計算式を利用して行う
③中古車の場合、耐用年数は法定耐用年数を越えるかどうかで計算式が異なるので注意する
④耐用年数に応じて減価償却を行うことができる
⑤減価償却する際は、「取得日」「再取得価額」「取得価額に含まれる費用」に注意して計上する
⑥耐用年数で中古車を購入するのであれば、普通自動車は経過月数が46ヶ月(3年10ヶ月)、軽自動車は16ヶ月(1年4ヶ月)が狙い目
中古車を減価償却する際、耐用年数はどう計算する?
中古車の耐用年数は、新規登録された時期からの月数によって決定し、簡便法を用いた計算式で求めます。
(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)
4年落ちの中古車(普通車)の耐用年数の計算式は?
(法定耐用年数6年)ー(経過年数4年)+(経過年数4年×0.2)
=2年+0.8年=2.8年
となり、1年未満を切り捨てるので4年落ちの中古車の耐用年数は2年となります。
事業用の中古車は何年落ちを買うのがお得?
耐用年数で中古車購入を考えるなら、経過月数が普通自動車は46ヶ月(3年10ヶ月)、軽自動車は16ヶ月(1年4ヶ月)が狙い目です。また、事業年度初月に購入すると全てを経費として計上できるのでおすすめです。
