ドライブ
更新日:2021.02.10 / 掲載日:2020.04.02
トラックの高さ制限には要注意!積載できる荷物の制限や罰則とは?
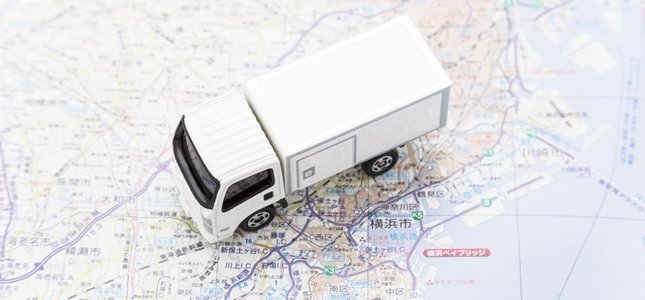
グーネット編集チーム
引越しや大型家電を運ぶときなど、荷物の高さや幅が荷台からはみ出したまま運転していませんか?
走行の安全性を保つために、車に積める荷物の高さや幅・重量の数値は法律で定められていて、これに違反した場合は罰則が科せられます。
ここでは、荷物のはみ出しや高さの制限について紹介していきます。
トラックの高さ制限とは?

グーネット編集チーム
道路法では車の高さや横幅など、実に様々な項目について詳しく定められています。
トラックの高さ制限に関しては、「原則3.8m以下」と規定されていました(道路交通法第22条)が、2004年の法改正により、「高さ指定道路」に限り、4.1mまで規制が緩和されました。
高さ指定道路とは、危険防止や構造保全の面での支障がないと認められ国が指定した道路のことです。さらに、「制限外積再許可」の手続きを取り認可されれば4.3mまでの荷物を運ぶことができます。
高さ制限を超えてしまうトラックの場合、荷物はどう運ぶ?
以上のように高さが規定されているものの、積載する荷物によってはどうしても既定の高さを超えてしまうケースが想定されます。
そのような場合にはどのようにして荷物を運べば良いのでしょうか?
制限を超えてしまう場合の荷物の運び方について紹介します。
「制限外積載許可」の手続きを行う
「制限外積載許可」の手続きを取れば、高さ4.3mまでの積載が可能になります。
制限外積載許可とは、高さや幅、長さなどに関する規定を超える荷物を運ぶ際に取らなくてはならない許可のことで、出発する地域を管轄している警察署で手続きを行うことができます(トラックの全長が12mを超えない場合や複数回往復しない場合には、交番や駐在所などでも手続きできます)。
制限外積載許可を取れば、以下の範囲までの荷物を積むことができます。
長さ:自動車の1.5倍の長さまで
幅:自動車+1m(全体で3.5m以内)
高さ:4.3m
また、制限外積載許可で認められる範囲が積載できる荷物の大きさの上限となっているので、この基準値を超える荷物に関してはどのような手続きを取ったとしても積載することはできません。
制限外積載許可の申請に必要な書類
制限外積載許可を取得するために必要な書類は以下の通りです。
・制限外積載許可申請書(インターネットからダウンロード可能)
・車検証コピー
・特殊車両通行許可証
・積載方法の概略図
・経路図
・申請者の免許証コピー
・道路管理者の通行許可証
申請から許可証の発行までに一週間ほどかかることもあるので、前もって申請の申し込みをしておくように注意しましょう。また、手続き方法も都道府県ごとに異なる場合もあるので、事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
高さ制限やはみ出し制限に違反したトラックへの罰則

グーネット編集チーム
高さ制限やはみ出し制限に違反したトラックにはどのような罰則が科せられるのでしょうか?
違反をしないことが大前提ではありますが、念のため確認しておきましょう。
100万円以下の罰金
所定の積載量をオーバーしてしまった場合や道路管理者の許可なく道路を通行してしまった場合、通行時に許可証を携帯していなかった場合などは、100万円以下の罰金が科されます(道路法第104条)。
免許証の加点
罰金に加えて免許証の点数も1点加点になります。さらに、過積載の場合には荷主や事業者にも罰則があります。荷主に対しては、管轄の警察署から再発防止命令が出され、それでも違反をした場合には6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されます。事業者に対しては、運行管理の資格取消や事業許可取消が課されることもあり、社会的信用を大きく損なってしまいます。また、事業主に対しても懲役刑や罰金刑が課されることがあります。
また、車両の通行が禁止または制限されている道を通行するなど、許可条件を違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。違反して車を走行させてしまうと、罰金どころか懲役刑に当たることもあります。過大な荷物の載積は絶対に避け、ルールを守った運搬を心がけましょう。
まとめ
交通の安全と道路の保全のために、トラックには重量や高さなどの制限が設けられています。
トラックの高さ制限は、原則としては3.8mまでですが「高さ指定道路」に限り4.1mまで、制限外積載許可を受けたトラックに対しては4.3mまでの高さまでが許可されます。
高さ制限に違反した場合には、ドライバーだけではなく荷主や事業者に対しても厳しい罰則が科されます。何より、安全面が大きく損なわれてしまうため、安全面を強く意識して正しく荷物を積載しましょう。
