車とお金
更新日:2019.10.29 / 掲載日:2019.10.29
3ナンバーの税金は高い?5ナンバーとの違いを解説!

グーネット編集チーム
クルマにかかる費用について「3ナンバーは税金が高くて、5ナンバーは安い」と認識している方も多いかもしれません。しかし、実は3ナンバーか5ナンバーかは、税金の金額と直接関わる内容ではありません。そのため、税金面から、3ナンバーではなく5ナンバーのクルマを選ぼうと考えるのは適切でありません。
ここでは、こういった「3ナンバー」と「5ナンバー」に関する勘違いを正すとともに、出費を抑えたクルマ選びができるよう、3ナンバーと5ナンバーのそれぞれの数字の意味をはじめ、クルマの税金についても触れながら、3ナンバーと5ナンバーの税金の仕組みなどについて解説していきます。
3ナンバーと5ナンバーとは何?
そもそも税金に関して間違った考え方が広まってしまっている原因は、3ナンバーと5ナンバーのそもそもの付け方について誤解があるせいかもしれません。まずはどのようにナンバープレートに記載されている数字が決められているのか、ナンバープレートの基礎知識から確認しましょう。
地名の隣に書かれた小さな数字の意味
ナンバープレートには複数の情報が記載されています。
まず、ナンバープレートの上部に書かれている地名。これは「使用本拠置」といって、そのクルマを使っている地域がどこかということです。なお、使用本拠置の地名の数は117種類あります。
使用本拠置の隣の小さな数字が「登録自動車の分類番号」です。
主に3桁の数字で表されていますが、1番左側にある数字がクルマの分類を示す番号で、右側の2桁はその中での番号なので基本的に意味はありません。
なお、1番左側にある数字が示すクルマの分類は、以下のようになっています。
1:普通貨物車(トラックなど、用途が貨物の普通自動車)
2:普通乗合車(バスのような定員が11名以上の普通自動車)
3:普通乗用車(乗車定員が10名以下の普通自動車)
4:小型貨物車(貨物用途の小型自動車)
5:小型乗用車(乗車定員が10名以下の小型自動車)
6:小型貨物車(三輪貨物車)
7:小型乗用車(三輪乗用車)
8:特殊用途自動車(パトカー、霊柩車など)
9:大型特殊自動車
0:建設機械
つまり登録自動車の分類が「小型乗用車」か「普通乗用車」で、分類番号の一番左側が「3」になるか「5」になるかが決まります。そして、分類番号の一番左側が「3」のものを「3ナンバー」、「5」のものを「5ナンバー」といいます。
3ナンバーか5ナンバーかを決める条件
3ナンバーか、5ナンバーになるかは、登録自動車の分類によると書きましたが、では、登録自動車の分類はどのように決まるのかを確認しましょう。
3ナンバーの「小型乗用車」と5ナンバーの「普通自動車」の分類方法は下記の4つの条件によって決まります。
・クルマの全長が4.70m以下である
・クルマの横幅が1.70m以下である
・クルマの高さが2.00m以下である
・クルマの総排気量が2,000cc以下である
上記4つの条件をすべて満たしているクルマが「小型乗用車」に該当し「5ナンバー」に分類されます。
この4つの条件のうち、1つでも条件を満たさないものがあった場合「普通乗用車」に該当し「3ナンバー」です。
勘違いしがちなポイント
あらためて強調しておきたいのは「4つの条件を”すべて満たしている”クルマが5ナンバーに分類される」という点です。
つまり総排気量が2000cc以下だからといって、必ずしも「5ナンバー」になるとは限らないわけです。例えば、クルマの幅が1.7メートル以上のクルマならば、その時点で、排気量がどれだけ小さくても、自動的に「3ナンバー」になります。
税金を理解するには、まずはこの点をしっかりと押さえておくことが重要です。
3ナンバーと5ナンバーの自動車税の仕組みとは?
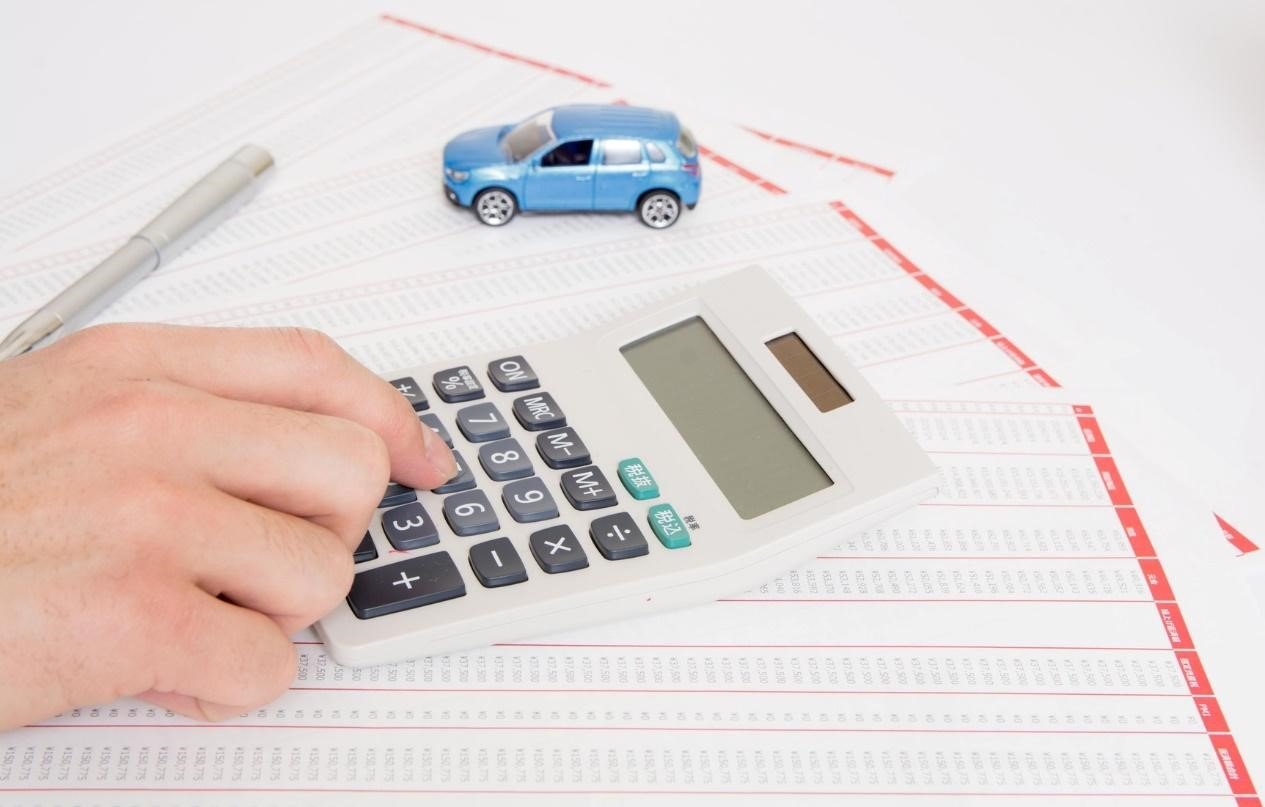
グーネット編集チーム
クルマにかかる税金は「自動車税」「自動車重量税」「消費税」の4種類で、それぞれ税率が決まる仕組みが異なります。
「消費税」に関しては、車両購入時にかかる税金でご存知かとおもわれますが、その他の税金に関しては、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。
ここでは「自動車税」「自動車重量税」についてご説明します。
自動車税
自動車税は、クルマを所有していることに対してかかる税金です。自動車税は毎年4月1日を区切りに課税され、同年5月末までに支払う仕組みになっています。
自動車税も自動車取得税と同様に地方税に分類され、クルマの所有者が住んでいる地域によって税金が変わります。
自動車重量税
自動車重量税は、クルマの重さによって税額が決まる税金です。自動車重量税は国税で、同じ重量であれば全国どこの地域であっても同じ税率となっています。
自動車重量税の納税が必要になるタイミングは車検を受けたタイミングとなっており、毎年払うとは限りません。
排気量が5ナンバーの基準でも税金が3ナンバーの金額になるのはなぜ?
クルマに関する4つの税金について解説しましたが、いずれの税金も登録自動車の分類によって決まるナンバーで税額が決まっているわけではありません。
例えば「自動車取得税」は「購入時の価格」によって決まり、
「自動車税」は「排気量」だけで決定するため、3ナンバーでも5ナンバーでも税金の金額が同じになる場合があります。
3ナンバーか5ナンバーかを決める条件は、「排気量を含んだ4つの基準を満たしているもの」が5ナンバーでした。そして、排気量は同じでも他の基準(主に車体の大きさ)が基準を満たさない場合は、3ナンバーになります。
そのため、排気量だけを見れば5ナンバーの基準を満たしている場合でも、実際に支払う税金が3ナンバーの金額になっている場合があります。
重量税とナンバーの関係
「重量税」の金額に関しても、クルマの重さで決まるため、分類番号との関連性は特にありません。
そのため、「クルマのサイズも排気量も小さいのに、とてつもなく重いクルマ」はあまり現実的ではないとはいえ、5ナンバーであっても重量が重かった場合は、3ナンバーの車種よりも重量税の金額が高くなることがありえます。
まとめ
ナンバーの決め方と、クルマにかかる税金の税率の決め方は異なるので、必ずしも5ナンバーより3ナンバーの税金が高くなるとは言い切れません。
さらに最近は、排気ガスや燃費の点で環境によいクルマは「エコカー減税」が受けられるケースも増えています。エコ性能が優れたクルマならば、減税になります。かなりエコ性能がよいならば、3ナンバーの税金がかなり安くなる、ということもあります。
上記をよく理解し、ナンバーだけにとらわれずに総合的に判断してクルマを選ぶようにしましょう。
