車のニュース
更新日:2024.12.10 / 掲載日:2024.12.06
いじめ報道に苦しむ日産 -前編-【池田直渡の5分でわかるクルマ経済】

文●池田直渡 写真●日産
日産自動車が上半期決算で営業利益が90%減の発表を行ったことはもう皆さんご存知だろう。日産がよろしくない状況にあるのは事実だが、取り上げ方が大袈裟すぎる。言ってみれば「熱が出て病院に行った」だけで「余命6ヶ月!」と騒ぐ様な流れ、もうほとんどイジメの絵柄である。
あちこちの記事を見ると、ひどい釣りタイトルのオンパレードだが、ダイヤモンド・オンラインに至っては「日産 -消滅危機-」と来るから恐れ入る。決算発表の動画すら見ていないのか、キャッシュフローの見方を知らない素人なのか不明だが、筆者はどっちかと言うとわかっていながら人の不幸を炎上させて食い繋ぐハイエナ的所業に見える。消滅というからには経営破綻を意味しているのだろうが、本当にキャッシュフロー的に追い詰められているとは思えない。
日産が発表した2024年度上期の財務実績
| (東京証券取引所届出) 中国合弁会社に持分法を適用 | 2023年度 上期 | 2024年度 上期 | 増減(対前回見通し) |
| 売上高 | 6兆633億円 | 5兆9,842億円 | -791億円 |
| 営業利益 | 3,367億円 | 329億円 | -3,038億円 |
| 売上高営業利益率 | 5.6% | 0.5% | – 5.1ポイント |
| 経常利益 | 4,127億円 | 1,161億円 | -2,966億円 |
| 当期純利益 | 2,962億円 | 192億円 | -2,770億円 |
さて、上期の決算発表会でCFO(つまり最高財務責任者)のスティーブン・マー氏は、キャッシュフローの状況について以下のように説明した。

「決算をご覧いただければ、ネットキャッシュは自動車事業でも1.3兆円と健全な水準です。流動性も健全で、未使用のコミットメントラインは1.9兆円。キャッシュ相当は1.4兆円。十分なキャッシュは確保できています」
当事者の発言を丸呑みするのではなく、「IRデータの主要財務推移」で裏どりをすると、確かに言う通りの以下のような数字が出てくる。ちなみに、カッコ内は、今年5月に発表した前年度(3月末〆)の、すなわち近年で突出した好決算当時の数字である。騒ぐほど減っていないことが確認できるだろう。ちなみにコミットメントラインとは、銀行などに確約をもらっている融資枠のことだ。
ネットキャッシュは1.3兆円(1.5兆円)、キャッシュ相当は1.4兆円(2.0兆円)。確かに前期から半年の間にネットキャッシュは2000億円、キャッシュ相当は6000億円減っているが、営業利益が90%減の今の状況がこのまま続いたとしても、手元の資金だけでここからまる一年以上は保つ計算だ(1.4兆円÷6000億円)。
さらに未使用のコミットメントラインが1.9兆円あるとも言っている。これは様々な条件によって発動しなくなることもあるので、常にあてにできるかどうかはともかく、額面通り割り算をすれば(1.4兆円+1.9兆円)÷6000億円で、5年半は保つことになる。この成績が5年半も続けば、どんな会社だって保たないのは当たり前で、キャッシュフローから見て、「日産 -消滅危機-」はほぼ誹謗中傷と言って良いレベルの針小棒大な釣りタイトルである。
とは言え、営業利益90%減の実態はどうなんだという声もあろう。可能な限り手短に説明しよう。
21世紀に入って中国マーケットは猛烈に躍進した。元々政治的にカントリーリスクのある国であるにもかかわらず、各社ともそのマーケットに頼った。ところがここ数年、中国政府は民族系メーカー優遇に大幅に振れたことで、外資系の自動車メーカーは総崩れ。日産も確かに大減速することになったが、これは日産だけでなく全ての外資が直面している問題である。
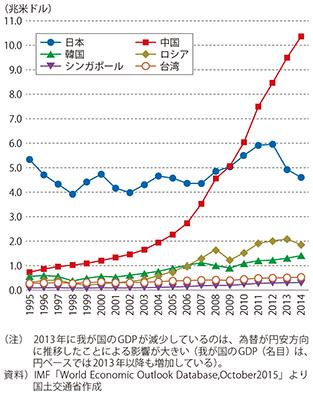
中国での成功に味を占めた各社は次の成長マーケットをいち早く確保しようとした。日産はASEANにターゲットを定め、インドネシアで1990年代から稼働している工場を拡張し、第2工場の増設を計画したのだが、投資する原資がない。そこで日米での新車投入費用を流用して投資にまわした。その結果2012年ごろを最後に、日米での新車のリリースが止まり。販売現場では古いクルマでビジネスを進めなければならなくなった。他メーカーから続々と登場する新型車に6年も7年も前に出た旧態然としたクルマで戦うには値引きしかない。

生命線である日米のビジネスでリスクを取ってまでギャンブルに賭けたASEANだったが、新興国の経済不調と、新興国ユーザーを舐めたクルマ作りで不発に終わり、2014年に増設した工場のみならず旧来の工場も一緒に2019年に閉鎖という結末に至った。ギャンブルの失敗である。
しかし被害はそれだけに止まらなかった。無理な販売が祟った日米では値引きの横行で利益を落とし、ついに日産は2019年2020年と2期続いて赤字決算となった。
2019年末に経営を引き継いだ内田誠CEOは、戦闘力をなくした旧型モデルを整理し、可能な限り新型車を投入。そこにたまたまコロナ禍の影響で半導体不足が勃発したことで、世界中の自動車メーカーの生産ラインが断続的に止まった。こうして市場の需要に対して供給不足が起きたタイミングで日産はモデルの入れ替えによる商品力向上を果たしたことによって、値引きを抑制しつつ、車両単価を引き上げるというミラクルを達成。それが今年5月発表の2024年度決算の好結果を生んだ。

しかし、それは単なる幸運に過ぎなかった。半導体不足がおさまって生産が伸び始めると、米国ディーラーにパニックが起きる。日本と違い、店頭在庫を販売する米国の方式では、品切れ状態ではビジネスができない。日本なら納期を相談しつつ、長期待ちを覚悟でクルマを買う客がいるが、米国では在庫がなければ他の店に行ってしまう。だから供給不足の間、米国中の全メーカーのディーラーが見込みの過剰発注を行った。奪い合いの構図である。
しかし、生産が回復すると、そうした過剰発注のクルマがどんどん入荷し始める。元々販売力を超えた発注をしているので、店頭にクルマが溢れる。置き場も無ければ、在庫資産が資金を圧迫するのだ。だからディーラーは一刻も早く在庫台数を正常化させようとバンバン値引きをして売る。自動車メーカーの利益率なんて良くて10%。5%もあれば合格ラインである。200万円のクルマを売って利益が10万円、20万円とかの世界。そこで値引き合戦を始めたら利益が消し飛ぶのは当然である。
しかし2012年から実質的な旧型モデルだけで戦わせ、ディーラーの営業パーソンに値引きのクセを付けたのも他ならぬ日産本社の戦略である。
半導体不足で定価販売ができている時に、頑張って値引きをしない販売を浸透させなければならなかった。特にその時期にほぼ定価で買った顧客に対しては、数ヶ月後に大幅値引きをするのは裏切り行為だ。新車を値引けば、中古車の市場価値も下がる。ロイヤリティユーザーの資産を傷つければ、次の買い替え原資が減って、結局その損は日産自身に返ってくる。ブランド価値を大事にする経営をもう一度取り戻せるかどうかが日産の今後を決める。
次週は引き続き日産の再生計画などを検証する。
