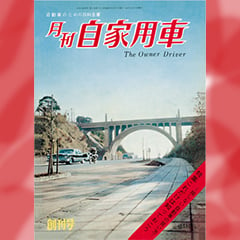車のニュース
更新日:2022.01.25 / 掲載日:2022.01.05
ついにトヨタが大攻勢! 国産BEVの近未来を読み解く
電動化への流れが一気に加速
国産BEV本格普及なるか?
トヨタは2030年に
BEV350万台体制へ
バッテリーに充電した電気でモーターを動かすBEVが、次世代のクルマの主役になるのは間違いないが、クルマの開発や販売体制、充電器の整備などのインフラ環境を含めて、多くの問題が山積み。そのためか、まだ遠い未来の話と思っているユーザーも多いだろう。
だが、欧州を中心とした世界市場では近々の問題として官民挙げて積極的に取り組んでおり、すでにBEVが販売の主力という国があるほどだ。
そんな流れもあって、日本国内でもBEVに対する議論が沸騰しつつあり、国内メーカーも各社なりになるが、具体的な計画を発表している。実際、2022年には数社の国内メーカーから本格的なBEVも発売されるのは確実だ。
まず具体的に力強いアクションが見えているのがトヨタだ。すでに2021年春にスバルとの共同開発のBEV(二次電池駆動電気自動車)として、bZ4XとBEV専用e-TNGAプラットフォームが発表し、2022年央を目処に製品車を発売することを告知していたが、さる2021年12月14日に「バッテリーEV戦略に関する説明会」を開催し、トヨタ/レクサスが展開するBEVモデルの最新情報を公開した。
説明会で展示されたBEVは合計16台。市販化発表も間近と思われるbZシリーズやレクサス・エレクトリファイドシリーズ、もう少し時間がかかりそうなコンセプトモデルまで、モデル開発の進捗具合には差があったが、トヨタとして具体的にBEVを開発しており、市販化目前のモデルが多数あることを大々的にアピールしたのだ。壇上から語りかける豊田章男社長も、開発中のBEVの製品化について「そんな先の未来ではない」と述べるなど、今後トヨタはBEVにも力を入れることを明言した格好。なおトヨタとしてはBEVのみに力を入れるわけではなく、水素燃料車のFCVやPHVなどのハイブリッド車、さらに水素エンジン搭載車の開発にも力を入れるという。BEVはあくまでもユーザーに対するクルマ選びの選択肢の一つとして考えているようだ。
同時に2030年のグローバル市場でのBEV年間販売台数として350万台を目指すことも明言。これはトヨタ全体の販売台数に対して3割ほどはBEVになるという計算になる。レクサスに関しても、2030年の年間販売台数を100万台、さらに全てのラインナップをBEVにすることも発表している。
もはやBEVへの
切り替えは止まらない
他メーカーもBEVへのシフトは加速する一方だ。温度差はあるものの、具体的なアプローチを見せている。
日産はいち早くリーフを発売した実績がある電動車のパイオニアメーカーだ。最近はリーフの開発で得た知見も注がれるシリーズハイブリッドのe-POWERがとても好調で、ノートなどの主力モデルに採用を進めることで快進撃を続けている。
日産は2021年11月29日に「Nissan Ambition 2030」を開催し、電動化を戦略の中核とする長期ビジョンを発表。内容としては2030年までにBEV15車種を含めた23車種の電動車を投入するというもの。その流れを受けたものとして、2022年に軽自動車のBEVが投入される。
このモデルは2019年の東京モーターショーに出典されたIMkコンセプトのプロダクトモデルで、三菱との共同開発モデルとして世に送り出される。モータースペックなどの詳細は非公開だが、春先にはその全貌が明らかにされるだろう。また大きな話題を集める電動SUVのアリアのデリバリーも始まる予定。電動車のパイオニアとして、今後も大きな存在感を保ち続けるだろう。
ホンダは2021年4月に四輪車の電動化の方針を発表。2040年までにすべての販売車両をBEVとFCVにする計画を明らかにしている。ホンダがエンジンを捨てるのか、ということで各方面に衝撃を与えたが、世界を取り巻くゼロ・エミッション化への要求を考えれば当然の判断ともいえる。電動車の目標台数は仕向地ごとに異なるが、日本国内は2030年に20%、2035年に80%、2040年に100%という比率を目指すとのこと。
マツダは2025年までに3モデル、25%の販売台数をBEVとして投入、スバルはトヨタとの共同開発車「ソルテラ」を皮切りに電動化を進め、2030年にはグローバル販売の4割を電動車にする。スズキも2025年を目処にBEVとハイブリッド車をグローバル市場に投入することを発表している
トヨタ、「バッテリーEV戦略に関する説明会」を開催


bZ4X
2022年央に発売
トヨタ車初の量販BEVとして発売されるbZ4X。ボディ形状は5ドアHB。車名の「X」が示すとおり、高い全高のクロスオーバーSUVとして開発されている。駆動バッテリーは床下に積載。そのためBEV専用に設計された「e-TNGA」が採用される。駆動方式はFF車と4WD車が設定され、FF車の駆動モーターはフロント150kW、4WD車は前80kW/後80kWのツインモーター仕様になる。バッテリー容量は71.4kWh。WLTC総合モードの航続距離はFF車が500km前後、4WD車が460km前後とされている。
Lexus RZ
北米でティザーサイトが開設
12月14日に「RZ 450e」として世界初公開。北米レクサスのティザーサイトなどを通じてエクステリアカットが公開されている。駆動方式や出力性能については不明だが、リヤのモデルナンバーの下には、かねてからレクサスが開発を進めている電動四輪駆動システム「DIRECT4」のプレートを確認できる。先に公開されたレクサスのコンセプトカー「LF-Z Electrified」で訴えた、最新の電動化技術と車両運動制御技術が高い次元で融合していることだろう。発売時期などは現時点では判明していないが、北米向けモデルは2022年下半期に発売される可能性が高い。
初披露も含む、合計16モデルを公開

bZ Compact SUV 
bZ Large SUV 
bZ SDN 
bZ Small Crossover

Lexus Electrified Sport 
Lexus Electrified Sedan 
Lexus Electrified SUV 
SPORTS EV 
Small SUEV 
Pickup EV 
Mid Box 
Micro Box 
Compact Cruiser EV 
Crossover EV

NISSAN IMk concept
2021年8月に軽クラスの電気自動車を2022年度初頭に発売することをアナウンス済み。まもなくデビューするプロダクトモデルは、2019年の東京モーターショーで発表されたIMk conceptをベースに開発されていることが予想できる。なおボディサイズは全長3395㎜、全幅1475㎜。全高1655㎜。バッテリーの総電力量は20kWh。実用的な航続距離を持つという。モーター出力に関しては不明だが、リーフ譲りの電動技術が注がれることで、軽自動車クラスとは思えぬほどの動力性能を発揮する可能性が高い。プロパイロットなどの日産の先進装備が装着されるのは確実だろう。購入者が支払う金額は公的な補助金により異なるが、実質的な購入価格は200万円~とされている。
NISSAN アリア
2021年6月に日本専用の限定モデルとして「limited」を専用予約サイトを通じて限定販売したが、11月からカタロググレードとしてアリアB6(2WD)の受注が開始された。限定モデルの「limited」と同様に専用予約サイトを通しての受付になるが、カタロググレードが用意されたことで、いま以上の注目を集めるのは間違いない。なおB6 limitedは、2022年1月27日に販売を開始、B6は2022年3月下旬に発売とされている。B6の価格は539万円になる。


SUBARU ソルテラ
トヨタとの共同開発で生まれたBEV専用プラットフォームを採用。bZ4Xとは姉妹車関係にあたるBEVだ。スバル自慢のAWDシステムにX-MODEやグリップコントロールなどの駆動支援制御も搭載されるなど、スバル車らしく悪路対応力に優れたモデルに仕上げられる。ソルテラ。なおソルテラのモデルネームの由来は、太陽を意味する「SOL(ソル)」と大地を意味する「TERRA(テラ)」から名付けられている。